太陰暦:月の満ち欠けに基づく古代の時間計測
太陰暦の原理と歴史
太陰暦は、月の満ち欠けを基準にした暦法で、古代メソポタミアや中国、そしてイスラーム世界で広く用いられました。この暦法は、人類が最も早く用いたとされ、占星術が行われていた文明で発展しました。現在でも、イスラーム暦(ヒジュラ暦)として太陰暦は使用されています。
太陰暦と季節のずれ
太陰暦では、1年を12の月の周期で計り、1ヶ月を約29.53日とします。これにより、1年は約345日となりますが、実際の太陽の公転周期である365日とのずれを修正するため、閏月を設ける太陰太陽暦がメソポタミアや中国で用いられました。
太陽暦への移行
太陽暦はエジプト文明で始まり、ユリウス暦を経てグレゴリウス暦が作られ、現在広く使用されています。日本も1872年(明治5年)に太陽暦に切り替えました。イスラーム世界では、11世紀のセルジューク朝でジャラーリー暦が作られたものの、イスラーム暦は今日も太陰暦を維持しています。
イスラーム世界の暦法
イスラーム世界では、『コーラン』に基づき、月の数を12と定め、そのうち4ヶ月を神聖月とする太陰暦が用いられています。農作業には適さないため、実際には太陰暦とグレゴリオ暦(太陽暦)が併用されています。この伝統は、宗教的な行事と日常生活の時間を区別する重要な役割を果たしています。
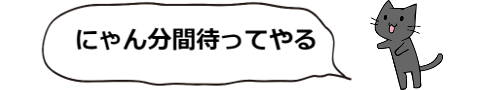
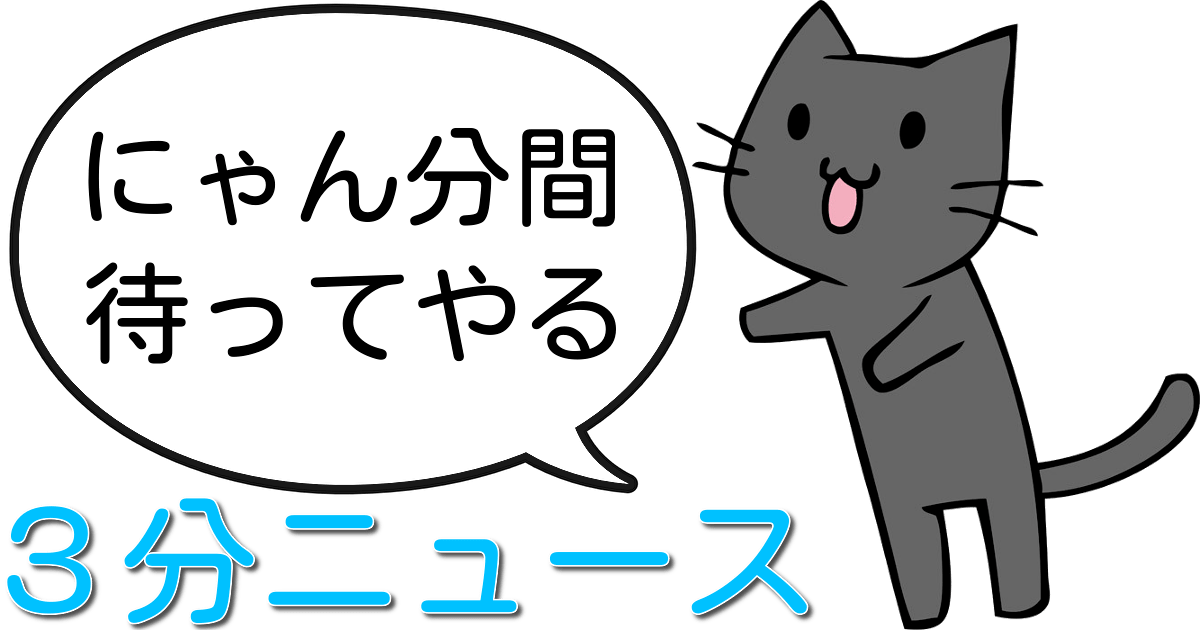
コメント