水泳の自由形は、ルール違反をしない限りはどんな泳ぎ方をしても良い競技です。しかし、ほとんどの選手がクロールで泳ぎます。なぜでしょうか?実は、クロールは速さだけでなく、持久力も備えているからなのです。この記事では、水泳の自由形がクロールで泳がれるようになった歴史と、クロールよりも速い泳法があるにもかかわらず、なぜクロールが主流であるのかについて解説します。
水泳の自由形の歴史
水泳の自由形は、1896年に開催された第1回アテネオリンピックから正式種目に採用されています。当時は、水泳には自由形しか種目がありませんでした。そして、全員が平泳ぎで参加していました。その理由は、息継ぎという概念がなく、顔を水につけないで泳ぐ平泳ぎが主流だったからです。
その後、息継ぎをしないでより速く泳ぐ方法として背泳ぎが誕生しました。背泳ぎは平泳ぎよりも速いことから、自由形に背泳ぎで出場する選手が増えました。しかし、背泳ぎは水しぶきを立てて泳ぐことから、オリンピック委員に美しくないと批判されました。また、伝統ある平泳ぎを守りたいという考えもありました。そのため、1900年に開催された第2回パリオリンピックでは、背泳ぎを独立種目として自由形と分けました。これにより、自由形は再び平泳ぎが主流となりました。
しかし、平泳ぎの主流も長くは続きませんでした。1904年に開催された第3回セントルイスオリンピックで、クロールが登場しました。クロールは、息継ぎをしながら泳ぐことで、平泳ぎや背泳ぎよりも速く泳ぐことができました。クロールが登場したことで、自由形にクロールで出場する選手が増えました。しかし、今度は平泳ぎを守るために、平泳ぎを独立種目として誕生させました。これにより、自由形はルール違反をしない限りはどんな泳ぎ方をしても良い競技となりました。そして、クロールが最速の泳法として君臨し続けることとなりました。
日本にクロールという泳ぎ方が伝わったのは、1912年に開催された第5回ストックホルムオリンピックでした。当時の日本の最速の泳ぎ方は横泳ぎでしたが、クロールには敵わず、惨敗しました。その後、日本人選手がクロールを学び、日本へと持ち帰りました。そして、1928年に開催された第9回アムステルダムオリンピックで、日本人選手が初めて金メダルを獲得しました。
クロールよりも速い泳法があるのに、なぜクロールが主流なのか?
クロールは、100年近く最速の泳法として自由形を支配してきました。しかし、2000年に開催された第27回シドニーオリンピックで、クロールよりも速い泳法が登場しました。それが、ドルフィンクロールです。
ドルフィンクロールは、クロールとバタフライの泳ぎ方を合体させたものです。手はクロールの動きをし、足はバタ足ではなく、バタフライのドルフィンキックの動きをします。この泳ぎ方は、オーストラリア代表のマイケル・クリム選手によって実践されました。クリム選手は、男子の100メートルリレーの決勝戦で、最後の数メートルをドルフィンクロールで泳ぎ、世界記録を更新しました。
ドルフィンクロールは、クロールよりも速い泳法ですが、なぜ自由形の主流にならないのでしょうか?その理由は、ドルフィンクロールは体力の消耗が激しいからです。ドルフィンクロールは、足の動きが大きく、水抵抗が大きいため、泳ぐのに多くのエネルギーを必要とします。そのため、最後まで泳ぎ切ることが難しいのです。実際に、クリム選手もドルフィンクロールで泳いだのは、最後の数メートルだけでした。
そのため、自由形でクロールが主流となっているのは、単純に速いからではなく、持久力と速度の両方を兼ね備えているからなのです。しかし、ドルフィンクロールが最速であることは披露されたのですから、今後は自由形で最後の数メートルを同じように泳ぐ選手が現れるかもしれませんね。
まとめ
水泳の自由形は、ルール違反をしない限りはどんな泳ぎ方をしても良い競技です。
自由形がクロールで泳がれるようになったのは、クロールが最速の泳法だったからです。
クロールよりも速い泳法としてドルフィンクロールが誕生しましたが、体力の消耗が激しく、最後まで泳ぎ切ることが難しいからです。
クロールが主流であるのは、速さだけでなく、持久力も備えているからです。
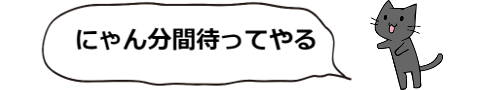
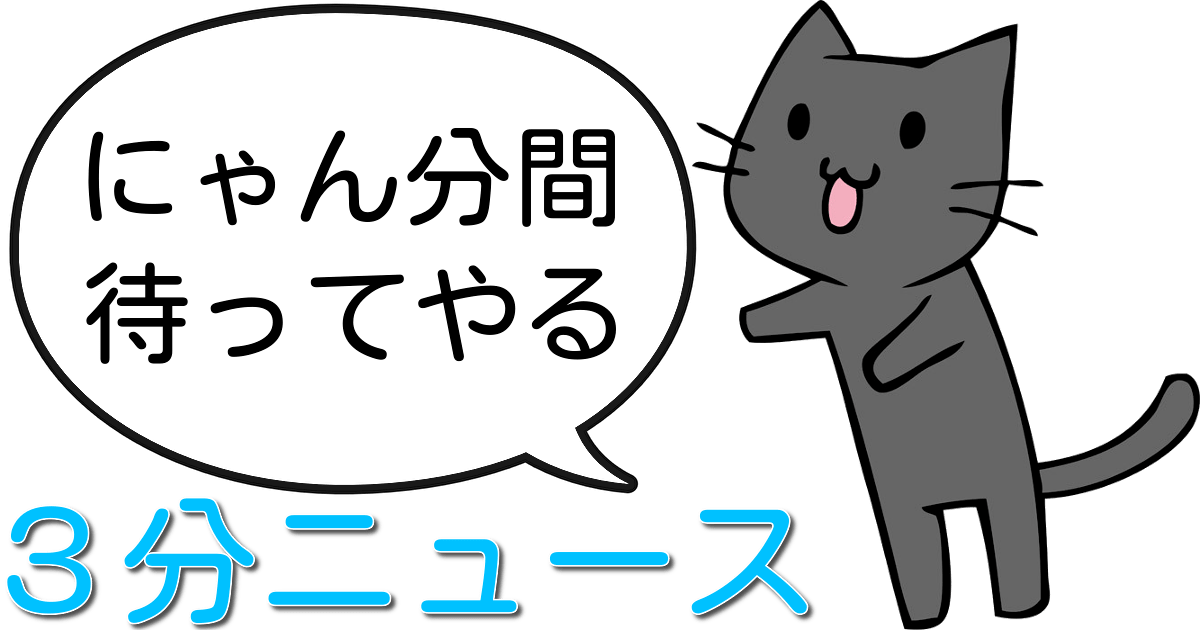
コメント