お菓子にまつわる雑学を紹介するこの記事では、「3時のおやつ」の歴史と健康効果について解説します。現代では「3時のおやつ」という言葉が定着していますが、なぜ3時におやつが食べられるようになったのでしょうか? 実は、この風習は江戸時代からあるもので、おやつを食べる時間として最適だとされています。
おやつは食事のことだった
「おやつ」という言葉が誕生したのは江戸時代のことでした。当時は2時~4時の間に取る食事を「おやつ」と呼んでいました。この時間帯のことを「八つ刻(やつどき)」と呼んでいたことから、「八つ刻に食べるからおやつ」という意味になりました。
現代では1日3食が定着していますが、昔の日本人は1日2食が当たり前だったとされています。朝食と夕食の2食しかなかったので、農作業や仕事の休憩中に間食を取ることもあったそうですが、「おやつ」という概念はありませんでした。江戸時代中期になると、人々の生活が豊かになり、「八つ刻」に間食を取る生活が根付き始めました。そして、「朝食」「おやつ(間食)」「夕食」という1日3食が取られるようになったのです。
また、この時代には白砂糖の製法が確立したことから、和菓子を扱った店も多くみられるようになりました。「おやつ」は朝食と夕食の間に食べる軽い食事のことでしたが、おやつにはこうした和菓子が食べられることも多かったそうです。そのため、その頃からおやつの時間に甘い物を食べるという風習が存在していたのです。
3時のおやつが定着したきっかけ
「おやつ」の時間帯は元々は「八つ刻」である2~4時でした。それでは、いつから「3時のおやつ」が定着するようになったのでしょうか?
3時のおやつというフレーズが定着するようになったきっかけは、1960年代に放送が始まった「文明堂のカステラ」のテレビCMだと考えられています。このCMはかなり長い期間にわたって放送されていたことから、現在30歳以上の方は一度はこんなCMソングを耳にしたことがあるのではないでしょうか。
♪カステラ一番、電話は二番、三時のおやつは文明堂
それまでにも、昼食と夕食の間の小腹の空く時間帯におやつを食べる食文化はありました。しかし、「3時のおやつ」というフレーズを広く浸透させたのはこのCMソングだったとされています。
3時のおやつは健康的
実は午後3時におやつを食べるのは、他の時間帯におやつを食べるよりも健康的だとされています。
人間の身体には「BMAL1(ビーマルワン)」と呼ばれるタンパク質が備わっており、これは別名「肥満遺伝子」とも呼ばれています。「BMAL1(ビーマルワン)」は脂肪を貯め込もうとする性質を持っていますが、この活動が低下するのが10~16時だとされています。そのため、10~16時は、他の時間帯に比べておやつなどの高カロリーで甘いものを食べても太りにくい時間帯であるというのです。
「八つ刻」に食べられていたことから、たまたま3時の風習として定着したおやつですが、意外にもこの時間にたべるおやつは理に適っていたんですね。
(しかし、いくら食べても太らないということではないので、くれぐれも食べすぎには注意してくださいね…。)
逆におやつを食べてはいけないとされる時間帯は22時以降から深夜にかけてです。この時間帯は最も「BMAL1(ビーマルワン)」が活発に活動するため、脂肪が最も増えやすい時間帯でもあります。ダイエットにおいては「朝食をたくさん食べて夕食を控えるようにする」ということをよく耳にしますが、実はこのような根拠もあったのです。
しかし、寝る前になると口寂しくなって、どうしても小腹が空いてしまうことってありますよね? そんな時はおやつなどの甘い物を食べることは避けるようにして、なるべく低カロリーのものを食べるようにしましょう。どうせおやつを食べるなら、体重を気にしないで食べられる午後3時に食べた方が、より美味しく味わうことができますよね。
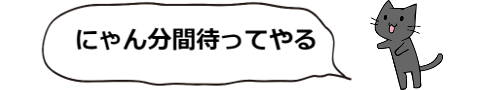
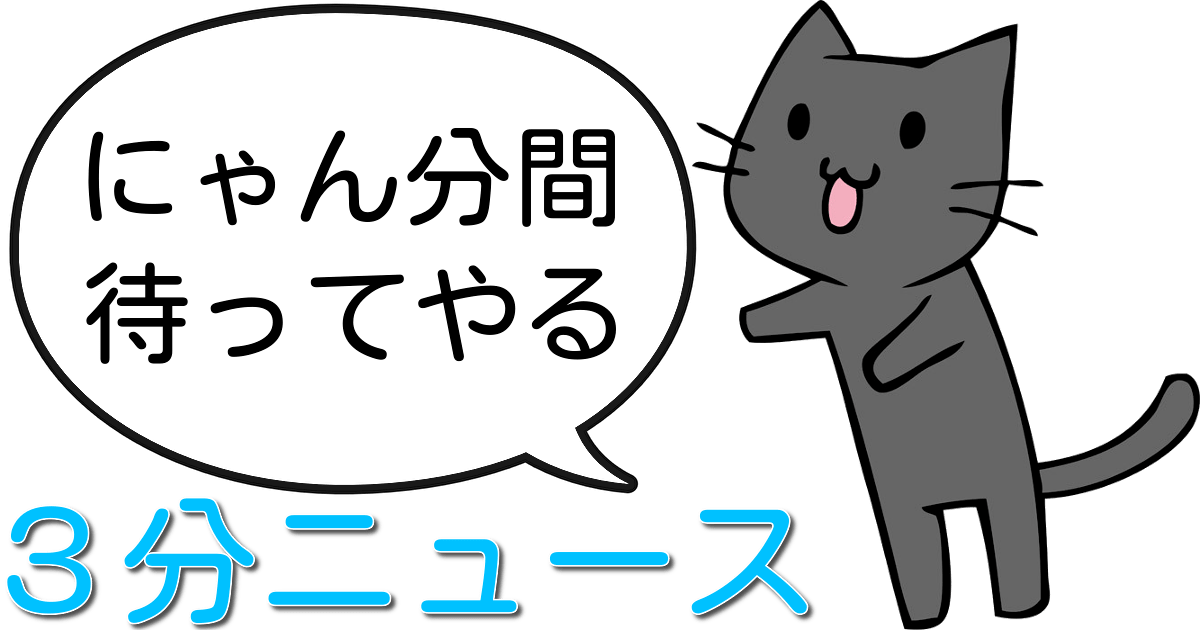
コメント